
「つみたてNISAで投資信託やってるし、分散できてるよね?」
そんなふうに思ってるあなた――
実は“資産クラスの分散”が抜けてるかもしれません。
株式だけじゃ守れない局面がある。
そこで登場するのが、
“無口な守護神”こと金(ゴールド)投資です。
金の投資って、ドラマや映画に出てくるような金の延べ棒を買うの?
あれって金持ちの特権みたいなもんでしょっ😎
僕なんかじゃ、砂金すら買えないよ😱
でも実は、金投資ってオルカンみたいに簡単に始められるんです。
しかも、株や不動産みたいに「増やす」資産じゃなくて、インフレや円安、株価暴落のときに黙って価値を守ってくれる“静かな盾”🛡️
この記事では、株+金の相性抜群な金投資の始め方を、わかりやすく解説します✨
✅ 第1ステップ:株だけだと危険?金が“守り”に強い理由
「つみたてNISAでオルカン買ってるし、分散できてるよね?」
そう思ってる人、多いと思います。
でも実は、“株式の分散”と“資産クラスの分散”は別モノなんです。
オルカンやS&P500は、確かに世界中の企業に分散してるけど、
どちらも“株式”という1つの資産クラスに偏っている。
つまり、株式市場が全体的に下落したら、どれも一緒に沈む可能性があるんです😨
そこで登場するのが、株と逆の動きをしやすい“金(ゴールド)”
金は企業の業績に左右されず、インフレや地政学リスクに強い。
「株と金って、なんで一緒に持つといいの?」
その答えはズバリ、動きが真逆になりやすいからなんです💡
たとえば、株式市場が大きく下落したときって、
ニュースやSNSでは「景気悪化!」「不安拡大!」
って言葉が飛び交いますよね📺💥
そんな時、人々はどうするかというと──
「安全な資産に逃げよう!」と考えます。
つまり、金(ゴールド)にお金が集まりやすくなるんです🏃♂️💰✨
金は「有事の金」と呼ばれるほど、
戦争・インフレ・経済危機など“世の中が不安定な時”に買われやすい存在。
📊 株 vs 金 比較表
| 項目 | 株式投資 | 金投資(例:金ETF) |
|---|---|---|
| インカムゲイン | あり(配当)銘柄による | なし🙊 |
| インフレ耐性 | 弱め(コスト増で利益圧迫) | 強い(価値保存に強い) |
| 値動きの激しさ | 大きい(景気に連動) | 比較的安定(守りの資産) |
| 地政学リスクへの強さ | 弱い(企業活動に影響) | 強い(有事に買われやすい) |
| 向いている人 | 増やしたい人📈 | 守りを固めたい人🛡️ |
※金も短期的には値動きがありますが、株ほど景気に連動しないため、“異なる動き”をすることが分散の鍵になります。
🧠 こんな人に金投資は向いている
- 株式だけでは不安を感じる人
- インフレや円安に備えたい人
- 長期で資産を守りたい人
- 「守りの資産」をポートフォリオに加えたい人
💬「株は“攻め”の資産。金は“守り”の資産。
サッカーで言えば、株がフォワードなら、金はゴールキーパーです。
点を取るだけじゃ勝てない。守りも必要なんです⚽🛡️」
✅ 第2ステップ:金投資の方法は4つ!あなたに合うのはどれ?
「金ってどうやって買うの?」
実は、金投資にはいくつかの方法があります。代表的なのはこの4つ👇
🟡 ① 金ETF(上場投資信託)で金を買う
- 特徴:証券口座から株を買う感覚で「金」に投資できる📈
- メリット:リアルタイムで売買できる・手数料が安い
- デメリット:配当なし/価格変動がある
- 代表銘柄:
┗ 1326 SPDRゴールド・シェア
┗ 1540 純金上場信託(田中貴金属)
💡 初心者におすすめ! 手軽で流動性も高く、ポートフォリオに組み込みやすい
🟡 ② 純金積立(毎月コツコツ)
- 特徴:1,000円〜など少額から積み立て可能💸
- メリット:ドルコスト平均法で価格リスク分散/自動積立でラク
- デメリット:買付手数料がETFよりやや高め/すぐには売れない場合も
- 有名サービス:楽天証券・マネックス証券・田中貴金属 など
💡 長期でコツコツ派におすすめ! インフレ対策や資産保全に向いてる
🟡 ③ 現物(金貨・延べ棒)を買う
- 金の延べ棒やコインを直接購入・保有✨
- メリット:有事にも安心/資産として実感がある
- デメリット:保管場所が必要(盗難・火災などのリスク)/購入コストがやや高め
💡 “有事の備え”として持ちたい人向け! ただし、保管コストや売却時の手間も考慮
🟡 ④ 金の先物取引(上級者向け)
- 特徴:将来の価格を予想して売買する「短期向け」取引📉📈
- メリット:レバレッジをかけて少額で大きな取引ができる(ハイリターンの可能性)
- デメリット:損失も大きくなるリスクあり/価格変動が激しく、初心者には難易度高め
- 向いている人:デイトレ・スイングトレード経験者やプロ志向の方
- 代表市場:大阪取引所・CME(米国)など
💡 短期トレード派・上級者向け! ハイリスク・ハイリターンの世界
❗初心者がうっかり手を出すと、大きな損失につながることも。くれぐれも慎重に!
⚖️ どれを選べばいい?
| 投資方法 | 最低投資額 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 金ETF | 約5万円~(1326など) | 手軽・売買簡単 | インカムなし |
| 純金積立 | 月1,000円~ | 積立でリスク分散 | 手数料が高め |
| 金地金(延べ棒) | 数十万円~ | 実物資産として保有 | 保管が必要・スプレッド大 |
| 金先物・CFD | 数万円~ | レバレッジあり・短期向き | ハイリスク |
※2025年7月時点の価格目安
💬「金投資って、実は“守り”だけじゃなく“攻め”にも使える。
ETFや積立なら守りの資産。先物なら短期の攻め。
つまり、金は“守備的MF”みたいな存在。守りながら、時に攻めもできる⚽✨」
💡初心者さんには「ETF」か「純金積立」が安心!
「株みたいに買いたい人 → ETF」
「コツコツ派・積立NISA感覚で → 純金積立」がおすすめです🙆♀️
僕もいずれは金を実物で保有してみたい😅
📉金投資は“インカムゲインゼロ”?
インカムゲインとはカンタンに言うと、
“投資から定期的に入ってくるお小遣い”みたいなもの。
株でいうと「配当金」
債券でいうと「利息」
がそれにあたります💸
でも…金(ゴールド)は、このインカムがゼロなんです😅
つまり、持っているだけでは配当も利息も一切もらえません。
「え〜!配当もらえないの?それって投資としてどうなの?」とビックリするかもしれませんね。
でも、ここで一息☕️
考えてみてください。
金は配当の代わりに…
「眠っていても価値がゼロにならない“お守り”」なんです。
お金が増え続けるわけじゃないけど、減らない安心感がある、って感じですね。
まるで…
「ボーナス出ないけど、絶対リストラされない会社」みたいなもの😂
(これ、案外すごくないですか?)
だから、金は「株の配当金狙い」とは別の役割。
リスクヘッジ=守りの資産としてポートフォリオに加えるのがベストなんです👌
✅ 第3ステップ:金投資の注意点!始める前に知っておきたいこと
「金って“守りの資産”で安心って聞いたけど…ほんとにノーリスクなの?」
──残念ながら、そんな“夢のような投資”は存在しません😅
金にもちゃんと“落とし穴”があります。でも、知っていれば怖くない!
ここでは、金投資でよくある注意点をやさしく解説していきます🛡️
🧾 ① 手数料にご用心!知らないうちにジワジワ…
金は「持ってるだけで安心」って思いがちですが、実は…
持ってるだけで“ちょっとずつお金が減る”こともあるんです💸💦
| 投資方法 | 手数料の例 |
|---|---|
| 金ETF | 売買手数料+信託報酬(年率0.4〜0.5%) |
| 純金積立 | 買付手数料+スプレッド(買値と売値の差) |
| 金地金 | 購入手数料+保管料(貸金庫など) |
| 金先物 | 取引手数料+証拠金管理のコスト |
💬「金は“お守り”だけど、ちょっと高級なお守りかも…😇」
🧾 ② 税金の扱いがバラバラ!知らないと損するかも?
「金ETFなら株と同じでしょ?」と思ってる方、ちょっと待って!🚨
実は、金の種類によって税金の扱いが違うんです。
| 投資方法 | 税制の扱い |
|---|---|
| 金ETF | 株式と同じ(申告分離課税・約20%) |
| 純金積立・地金 | 雑所得扱いになることも(総合課税) |
| 金先物 | 先物取引の税制(申告分離課税) |
💡補足:「金ETF」以外の金投資は、利益が20万円を超えると確定申告が必要になる場合があります。口座の種類(特定口座/一般口座)によっても異なるので確認を。
💬「同じ“金”でも、税務署の見方はバラバラ。まるで“金の多重人格”😅」
🧾 ③ 保管リスクって…リアルに怖い
金地金(延べ棒やコイン)を買うと、“物理的に守る”必要があります。
自宅に置いておくと…火災・盗難・うっかり紛失など、リスクがいっぱい🔥🕵️♂️💨
💬「金を枕の下に入れて寝るのは…映画だけにしておきましょう😂」
🧾 ④ 値動きのクセを知ろう!“守り”でも上下する
金は配当も利息もないので、値上がり益だけが収益源。
インフレや地政学リスクで上がることが多いけど、
景気が回復すると「金より株!」ってなって、下がることも📉
💬金は“守備的MF”だけど、時々ベンチに下げられることもある⚽😅
🧾 ⑤ 短期トレードは慎重に!先物は“プロの領域”
金先物は、レバレッジをかけて少額で大きな取引ができるけど…
その分、損失も大きくなるリスクあり⚠️
初心者がいきなり飛び込むと、まるで「初めてのスキーでいきなり上級コース」状態⛷️💥
💬「まずは“雪だるま作り”から始めましょう☃️(=ETFや積立)」
✅ まとめ:金は“安心”のために、まず“知識”を!
「金投資は安心感が魅力。でも、安心するには“知識”が必要。
手数料・税金・保管リスク──知らないと損することもあるけど、
知っていれば“守りの資産”として、あなたのポートフォリオをしっかり支えてくれます🛡️✨」
🎯 番外編:出口戦略を作ろう!金投資は“買ったら終わり”じゃない
「金って、買ったら安心でしょ?ずっと持ってればいいんじゃない?」
──それ、ちょっと危険です⚠️
金はインカムゲイン(配当・利息)がゼロ🙊
つまり、持ってるだけではお金を生まない“無口な資産”。
だからこそ、売却タイミング=出口戦略がすべてなんです。
間違えると、ただ持ってるだけでコストがかかる“重たい資産”になってしまいます💸💦
🛤️ 金投資の出口戦略:キャピタルゲインでどう図る?
✅ 1. 価格上昇時に売却して利益確定
- 金価格は景気後退・インフレ・地政学リスクで上がりやすい
- 逆に、金利上昇・ドル高では下がりやすい
- → 「売るべきタイミング」は、経済の不安がピークに達した頃
💬世の中がざわついてるときこそ、金が輝く。
でも、輝いてるうちに売らないと、ただの“眩しい塩漬け”に…😅
✅ 2. ポートフォリオの調整として売却
- 株式が回復してきたら、金を減らしてリスク資産に戻す
- →「守りの金」から「攻めの株」へシフトする出口戦略
💬「金は“守備的MF”。でも、試合展開によってはフォワードにパスしてあげよう⚽✨」
✅ 3. 長期保有で“保険”として維持する選択も
- キャピタルゲイン狙いではなく、資産防衛目的で一部を残す
- →「売らない出口」もあり得る(ただし保管コストに注意)
💬「金は“非常口の鍵”。使わないかもしれないけど、持ってるだけで安心する存在🔑」
💡 出口戦略の考え方
- 「〇〇円になったら売る」など、価格目標を決めておく
- 「株が〇%回復したら金を減らす」など、状況ベースで調整する
- 「一部は保険として残す」など、目的別に出口を分ける
💬「出口を決めずに金を買うのは、地図なしで山に登るようなもの。
登ったはいいけど、降りられない…ってなる前に、ルートを決めておこう🗺️」
⚠️ 注意点:出口戦略がないとこうなる
金投資は、買うのは簡単。でも、売るタイミングを決めてないと、ただの“重たいお守り”になってしまいます。
だからこそ、目的と出口をセットで考えるのが、金投資の鉄則。
あなたの資産を守るために、“出口戦略”という名の地図を持っておきましょう🛡️✨
🏁 最終ステップ:金投資まとめ編|買い方・選び方・出口まで完全ガイド
🪙 金投資は「目的」と「出口」がすべて
金はインカムゲインがない分、“なぜ買うか”と“いつ売るか”が超重要。
ただ持ってるだけでは、コストがかかる“重たい資産”になってしまいます。
🧭 ここまでの流れを振り返り
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 買い方編 | 金投資の手段(現物・ETF・純金積立) | 初心者はETFが手軽でおすすめ |
| ② 選び方編 | 金ETFの比較(1540・1328・1326) | 信託報酬・保管形態・流動性をチェック |
| ③ 出口戦略編 | 売却タイミングの考え方 | 経済不安のピーク・ポートフォリオ調整・保険的保有 |
| 番外編 | 金ETFは“出口戦略”が命 | キャピタルゲイン頼みだからこそ、出口設計が必要 |
🧾 証券会社別・金ETF取り扱い一覧
| 証券会社 | 取り扱いETFコード | ETF名 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 松井証券 | 1540、1328 | 純金上場信託、金価格連動型ETF | 国内ETF中心。初心者向け。 |
| auカブコム証券 | 1540、1328、1326 | 純金上場信託、金価格連動型ETF、SPDRゴールド・シェア | 国内+海外ETF対応。長期保有にも◎ |
🚀 まとめ:金投資は「買って終わり」じゃない
金は“守りの資産”だけど、守るだけじゃ資産は育たない。
「買う理由」と「売るタイミング」をセットで考えることで、金投資は初めて“意味のある選択”になる。
🚀 まずは口座開設からスタート!
金ETFは「買える証券会社」が限られているからこそ、最初の一歩=口座開設が重要です。
以下のリンクから、あなたに合った証券会社を選んでみてください👇
金ETFは“守りの資産”、J-REITは“収益を生む資産”。
どちらも分散投資の選択肢として魅力があります。
J-REITについては、こちらの記事で初心者向けに解説しています👇
https://kabudou-eri.com/jreit-buy-rebalance-exit-strategy
「金価格の動向や市場の裏側をもっと知りたい方は、
日本貴金属マーケット協会(JBMA)のレポートも参考になります。
業界の最新情報やイベント情報も掲載されています。」

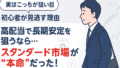

コメント